一人で荒野を歩いていた。
自分以外誰もいない荒野。
いつも夢に見る孤独な世界。
また、誰かの泣き声が聞こえていた。
どこか遠くから聞こえてくるようでもあり、すぐ近くで泣いているようでもあった。
ひどく体が重かった。
足は鉛のように重く、一歩動かすことさえ苦しかった。
だが歩き続けた。どこに行こうとしているのかも分からないが、とにかく歩き続けた。
前に進みたいのか……いや、もしかすると、何かから逃げているのかもしれない。
だがいったい、何から逃げているのだろう。もしかして、その泣き声の主から逃げているのだろうか。
分からない。
分からない。
リュウの魂はいまだ冥府の中にあった。
リュウの魂はいまだ行き先を決めかねていた。

レインハルトが辿り着いたのは、リュウが育った孤児院だった。ルークのいうとおり、孤児院とは名ばかりで貧民窟のような汚らしい建物だった。建物の前ではみすぼらしい格好の子供が三人、しゃがんで石ころで遊んでいた。レインハルトはその輪にはまるように腰を屈めた。子供たちはいきなり輪に入ってきたレインハルトを興味深げに眺めていたが、意外にも子どもたちの顔には卑屈さはなく、目は澄んで光があった。
「きみたちの名前は」
レインハルトは優しい声で尋ねた。
「……ベン」
三人の中で一番大きい少年が答えると、すかさず残りの二人が、
「テオ」
「ルイス」と元気に答えた。
レインハルトは三人を微笑ましく眺めながら、一番大きなベンという少年に尋ねた。
「ベンよ、君はこの孤児院にいたリュウという少年のことを知っているかね」
その途端、三人の眼が輝いた。
「リュウのことならよく知ってるよ」
「僕も知ってるよ」
「僕だって知ってるよ」
「ははは、ベンにテオにルイスよ。みんないい子だ。みんなリュウのことを知っているんだね。それじゃ、みんなに聞こう。リュウはどんな少年だったろうか」
「リュウは凄く強かったよ」
「剣技トーナメントで優勝したんだよ」
「王の騎士になるんだよ」
三人は誇らしげに答えた。
「もっと小さい頃のことはしらないかね。リュウはずっとここにいたのかね」レインハルトが重ねて尋ねた。
「……違うよ」
今度はベンだけが答えた。
「違う? では、リュウはいつここに来たのかね」
ベンは指をおって数えていたが、ようやく思い出したと見えて、大きな声で叫んだ。
「そうだ! 三年前だよ。思い出した。ちょうど僕が十歳になった年だったよ」
「……三年前」
レインハルトは一言つぶやいて、しばらくじっと考えこんでいたが、ふと気づくと三人の子どもたちが自分の顔をじっと見つめていた。
「すまん、すまん。ところで子ども達よ、きみたちはリュウのことは好きかね」レインハルトは苦笑しながら聞いた。
「大好きだよ。リュウは英雄だからね」
「僕も絶対にリュウのように強くなって、トーナメントで優勝するんだ」
「僕はリュウと一緒に悪い奴をやっつけてやるんだ」
そう答える子どもたちの顔はみな生き生きとして、目は光り輝いていた。レインハルトはその様子に満足したように立ち上がると、こう言った。
「ベンもテオもルイスもよく聞きなさい。リュウはそなたたちに誇りと勇気を与えたようだ。それを決して忘れてはいけないよ。そうすれば、きっと君たちもリュウのように強く立派な人になるだろう」
レインハルトの言葉を聞くと、三人も勢いよく立ち上がった。
「リュウを忘れるもんか」
「リュウはおじさんよりも強いんだぞ!」
「ところで、おじさんの名前はなんていうの」
レインハルトは思わず笑い声をあげた。そして三人の子どもたちに自分の名を告げた。
「私は預言者エトに選ばれた聖騎士レインハルト。神の御業をこの世に示せと命じられたものだ」
レインハルトがそう言うと、子ども達は驚きのあまり口をぽかんとあけて、目をぱちくりさせた。
「子ども達よ、よいか、決して忘れるなよ。道は自らが切り開くものだということを。そして、道を自ら切り開こうとする勇気あるものにこそ、神はその御手を差し伸べられるのだということを」
レインハルトは、固まったように突っ立っている三人の頭をそれぞれなでると、建物の入り口に向かっていった。レインハルトが建物の中に入る瞬間、後ろで子供たちが狂ったように大騒ぎする声が聞こえた。レインハルトはその歓喜に満ちた声を聞いて、思わず口がほころんだ。

レインハルトは施設長の部屋に通されていた。レインハルトの前には頭の禿げた少し神経質そうな司祭が緊張感を漂わせて座っていた。
「このような汚いところに聖騎士レインハルトにお越しいただけるとは……突然の訪問でしたので、何の準備もしておらず……満足なおもてなしもできませんで、なんとも申し訳なく……」司祭が額に汗を滲ませて弁明するようにいった。
「いや、私が勝手に立ち寄ったまでのこと。気遣いは不要だ」
「ところで……あの、今日はどのような御用で……」司祭はレインハルトを盗み見るように言った。
「先ごろ迄この孤児院にいたリュウという少年のことについて、いつくか尋ねたいことがあってまいったのだ」
「リュウ……リュウが、また何かご迷惑をおかけしたのでしょうか」
司祭は明らかに不安げな顔になった。
「いや、そうではない。リュウという少年がいつここに来たのか、どういった少年だったかを知りたいだけなのだよ」レインハルトは努めて優しく語りかけた。
司祭は、レインハルトの用向きがこの施設や自分への非難でないことを悟ると、ようやく安堵したようにほっと肩をなでおろした。
「そういうことでしたか――ええと、そうですね、確かあれは……少し、お待ちください」
司祭はいそいそと立ち上がると、書棚から綴りを取り出してきた。そして、ぺらぺらとページをめくっていくと、
「ああ、あった、ここにありました! ええと、ちょうど三年前の今頃、この施設に入所したようですね」
「それ以前はどこにいたのですか」
「……そういったことは何も書かれていないな……身寄りもないようだし……おっ、ここにメモがありました……ええと、身寄りがいないので、ここで預かってほしいと申し出があったと書かれています。どうやら、リュウを連れてここを訪ねてきたものがいたようです」
「それは誰ですか」
「ええと、その人のサインがあるんですが、よく読めないな……」
「見てよろしいかな」
レインハルトは立ち上がると司祭の手元にあるページを覗き込んだ。レインハルトはそのサインを見た瞬間に全てを了解した。エトの手紙はやはり真実であった。そのページに書かれたサインはレインハルトもよく見知ったものだった。それは預言者エトのサインだった。
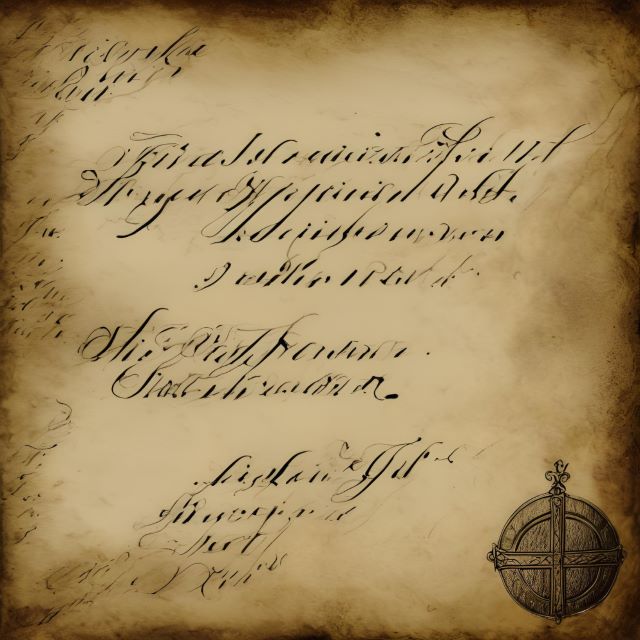
レインハルトは再び椅子に座ると、改めて司祭に尋ねた。
「リュウは、どのような少年でしたか」
司祭はどういったらいいか戸惑うようであったがどうにかしゃべり始めた。
「一言でいえば乱暴者でした。いつも喧嘩に明け暮れ、騒ぎを起こしていました。人と付き合うこともなく、一人で空ばかり眺めているような子でした。ですが妙に年下の子どもには慕われていて……つまり、なんですな。弱いものいじめが嫌いなんでしょうな。年上のものが年下のものをいじめると、それこそ、いじめた大きな子どもにつっかかっていって、終いには、小さいものをいじめるとリュウに殴られるので、この施設ではいじめはすっかりなくなってしまいましたよ」
レインハルトは、ベン、テオ、ルイスがリュウに対して非常な憧れをもっている理由がようやくわかったような気がした。
「――それで、すっかりこの孤児院はリュウが牛耳ってしまったんですが、そしたら今度は頻繁に外に出るようになってね。何か悪さでもしているんじゃないかとだいぶ心配したんですが、まさか剣術の稽古をしているとはね。リュウが剣技トーナメントで優勝して、王の騎士になる資格を得たと聞いた時は本当にびっくりして空いた口がふさがりませんでしたよ――まあ、そんなこともあって、この孤児院にもたくさんの寄付が舞い込み、偉い方の視察もあって、私どもも大いに喜んでいたんですが……まさか、警察署長に危害を加え、知事の息子を殺害するなんて……この孤児院の名声も天から地に堕ちたようなものですよ。もはや、この孤児院は終わりです。知事は決して私たちをお許しにはならないでしょう」
がっくりと肩を落とした司祭にレインハルトは声を掛けた。
「司祭殿、知事とはさきほど話をしてきたところだ。リュウには一切の罪はないと言明していた。もはや、この施設に対して不利な扱いをすることはなかろう……彼自身のためにもな」
最後の言葉はほとんどつぶやき声で司祭には聞き取れなかったようだが、司祭は急に息を吹き返したように身を乗り出してきた。
「それは、まことですか!」
「ああ、本人が自ら語った言葉だ」
「おお、神よ! あなたは私たちをお見捨てにはならなかったのですね。私たちの祈りが天に届いたのですね!」
司祭は夢を見ているかのように飛び上がって、神に祈りを捧げた。レインハルトはもはや長居は無用とみて、すっと立ち上がった。それを見た司祭はそそくさとレインハルトの前に進んで、まるで神を仰ぐかのごとくに頭を垂れた。レインハルトはそんな司祭に向かって重々しく言った。
「これだけは言っておく。この施設が存続できたのは、まさに神の思し召しによるものだ。だが、それはそなたたちを愛した故とは限らない。司祭殿、子どもたちの希望を失わせるようなことがあっては決してならぬぞ。もしそのようなことがあれば、神もこのレインハルトも決してそなたを許さぬ。お分かりか」
さきほどまでの穏やかな口調とは違う、その雷鳴のごとき言葉は司祭の体を震わせた。司祭は神に叱責されたかのごとくに全身がぶるぶると震え、レインハルトが立ち去った後もしばらくの間頭を上げることができなかった。